このプロジェクトが目指すこと
コロナ禍によって影響を受けている、社会的に弱い立場の方々を応援すること
現金の直接給付ではカバーすることのできない、地域に根差したきめ細やかな支援を支えること
アフターコロナにも繋がる、「コミュニティの力で支えあう」関係性を築くこと
これまでに取り組んできた具体的なアクション
- ■開始~採択まで
- 2020年5月
- 基金設立・助成先団体の公募と寄付の受付を開始
- 2020年6月
- 説明会を実施
審査を実施、助成先団体が決定 - ■採択団体への支援
- 2020年7月
- 採択団体のプロジェクトページを公開
かけはし基金・各採択団体への寄付の受付終了。合計147件 2,406,760円の寄付が集まる
- 2021年3月
- 寄付募集開始
- 2021年10月
- 第2期助成先公募開始
- 2020年8月
- 二子玉川ライズS.C.との取り組みを実施
- 2020年10月
- 超福祉展2020にてセッション実施
プロジェクトの特徴
社会的に弱い立場にある方々を応援する基金であること

新型コロナウイルス感染症拡大による社会的な影響として、「格差を広げ、弱い立場にある人をより弱く」していることが挙げられます。
本基金は、コロナ禍においてのこうした現状を鑑み、特に子どもや高齢者、障がいを持つ方、ひとり親家庭や生活に経済的な不安を抱える世帯など、社会的に弱い立場にある方々を支えるために設立されました。
直接給付では支えられない、きめ細やかな支援を支える基金であること

例えばオンラインによる子どもの居場所づくり。例えば温かな食事を歩いていける範囲に届ける活動。たとえ規模は小さくても、「あなたは一人じゃない」「支える人が暮らしの傍にいる」という明確なメッセージ、そして生きる希望に繋がる活動が必要だと考えました。
かけはし基金は、こうしたきめ細やかな支援を、コミュニティの力で支える仕組みです。民間から自発的に始まった孤立と孤独を防ぐ活動を、共に支えることを目指しています。
アフターコロナの繋がりを重視していること

アフターコロナの時代にますます重要になるのは「気持ちの上でも、物理的にもそばにいてくれる人」、そして「支えあい、声を掛け合う関係性」です。
本基金では、自助とも公助とも異なる、「コミュニティの力で共に支えあう」関係性を築きます。そしてそれは、都市において普遍的に必要なつながりだと考えています。






これまでの歩み
さまざまな方のご協力を得て、第1期、第2期と支援を続けています。
第1期(2020年度)
支援先団体の審査と採択決定
基金開設と同時に、支援先の公募を実施し、4団体からの応募をいただきました。その後、外部審査員を含む下記3名の審査員による審査会をオンラインにて実施しました。
その結果、2つの団体が支援先団体として採択されました。
審査員からのコメントはこちらをお読みください。
<審査員>
- 平野覚治氏(ふきのとう・一般社団法人全国食支援活動協力会)
- 松本典子氏(駒澤大学経済学部教授)
- 水谷衣里(当財団代表理事)
採択団体
「生きづらさを抱えた子とその親が楽しく学び暮らせるまちづくり」
多様な学びプロジェクト@せたがや

特に新型コロナの影響で、不登校や発達障害など生きづらさを抱え始めた子に対し、子ども支援で実績のある方々が「楽しい学び発掘隊」として寄り添いながら、学びたいことや興味関心を見つけ、地域住民が「まちの先生」になって教えたり、地元のカフェや地域共生のいえがその場を提供するなどの活動をしています。
「せたがやこどもフードパントリー」
せたがやこどもフードパントリー実行委員会

世田谷区内で子どもや家族のために活動している団体が中心となり、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により生活が困窮している家庭の子どもたちに、食料を無償で提供しています。また合わせて、行政や民間団体との連携のもと、生活が困窮している家庭が利用できる様々な支援サービスに関する情報を提供し、必要な支援へのつなぎを行っています。
超福祉展への参加
2020年9月6日、ピープルデザイン研究所が主催するイベント「超福祉展」にて、「新型コロナと地域コミュニティのこれから~かけはし基金の経験から」というテーマでセッションを開催しました。
「超福祉展」は、障害者をはじめとするマイノリティや福祉そのものに対する「心のバリア」を取り除こうという趣旨で、毎年開催されてきたイベントです。
2020年は配信形式によるオンライン開催となりました。
アーカイブ動画もぜひご覧ください。
<登壇者>
- 水谷 衣里(当財団代表理事)
- 呉 哲煥(NPO法人CRファクトリー 代表理事)
- 松本 敬子(多様な学びプロジェクト@せたがや 代表)
- 齋藤 淳子(せたがやこどもフードパントリー 共同代表)
<セッションの概要>
- コロナ蔓延下で弱い立場にあるこどもや家族への支援をどう進めてきたか
- コミュニティ財団という役割が、どのような役割を発揮できたか
- withコロナ時代のコミュニティのあり方や展望
第2期(2021年度)
支援先団体の審査と採択決定
2020年度と同様、外部審査員を含む下記3名の審査員による審査会をオンラインにて実施しました。
その結果、1件が支援先団体として採択されました。
<審査員>
- 松村 克彦 氏(サイボウズ株式会社 社長室 クラウドソーシャルデザイナー)
- 鶴田 佳子 氏(昭和女子大学 人間社会学部 現代教養学科 教授)
- 土肥 真人(エコロジカル・デモクラシー財団 代表理事/東京工業大学 環境・社会理工学院 准教授/一般財団法人世田谷コミュニティ財団副理事長)
採択団体
「若者の自立のためのシェアハウス事業」
NPO法人すみれブーケ

2軒のシェアハウスにて6名の若者の社会的自立と再スタートを支援しているNPO法人すみれブーケは、コロナ禍の中、事業を継続していくために実施している独自のイベント「かみきたざわチャリティー」の運営を行っています。この取り組みを通じて、児童養護施設や里親家庭、自立援助ホームから巣立った若者で、社会での自立を目指し住む場を必要とする女性を支えることを目指しています。
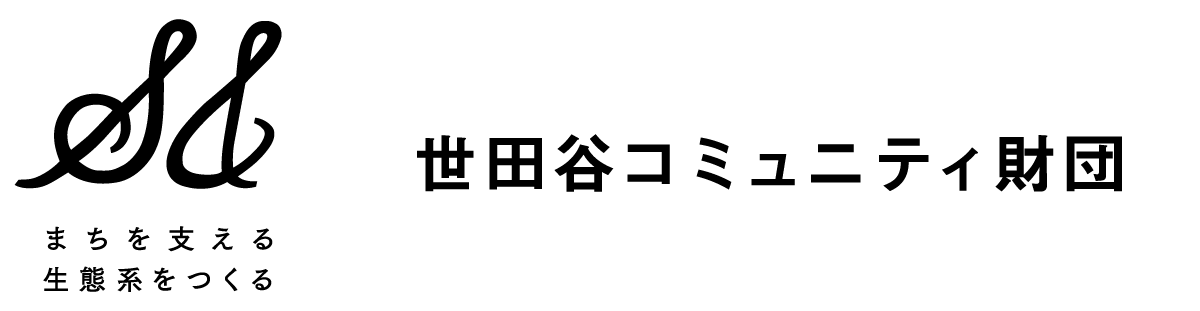


 詳細ページはこちら
詳細ページはこちら 紹介動画を見る
紹介動画を見る



























